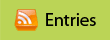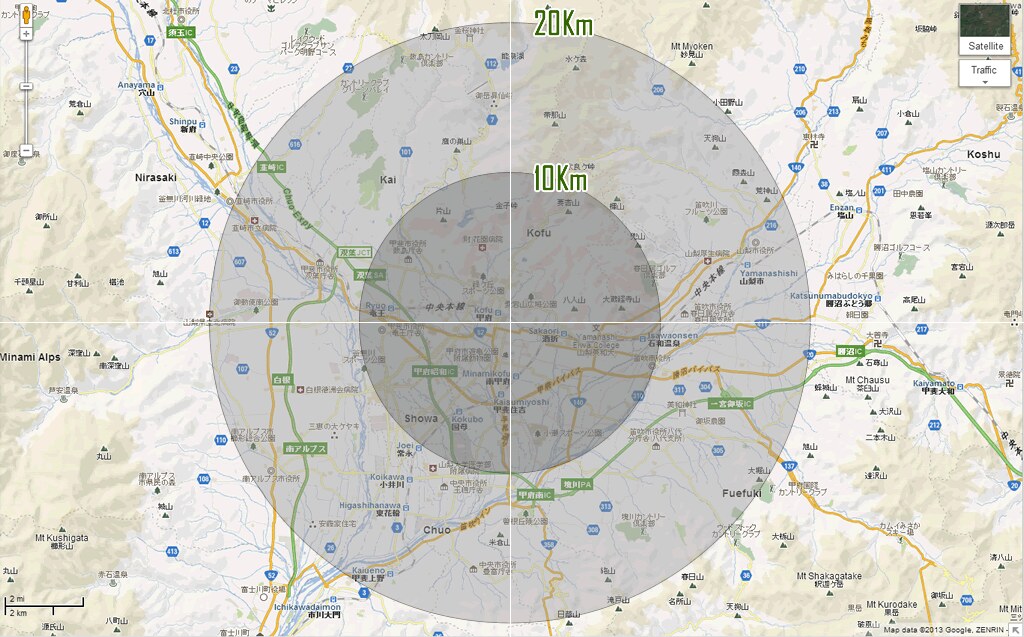唐突で鮮やかなイメージだった――はるか海上を白馬が走る。虐げられた女ミツの遠い故郷を歌う「相馬盆踊り」がそこに、流れる。浦山桐郎の『私が棄てた女』だ。福島県浜通り北部の相馬が津波によって被災し、更に放射性物質からの退避によって故郷=共同体の機能を奪われたとき、不意にこのミツの顔と馬の姿が浮かんできた。たしかに人は、断ち切られることを受け入れて生きているが、三月十一日の出来事はその「切断」の意味を超えてしまった。出来した悲劇に対して何が可能かと問う。確固としていた倫理の関係が超えられてしまったのだ。「映画」も「文学」もむろん「音楽」も何も可能ではない。そんな議論自体が無為だ。壁画に残された古代の人間たちの営為を辿りながら、スイスの美術史家ジークフリード・ギーディオンは、人間が初めて国家という予見し難い結末に至る組織を作ったとき、そこでは何が起こったのか、と問うた。その「結末」の姿を見なければならない日々が震災からの四ヶ月だ。福島第一原発の徹底的に憎悪すべき事故は地震の併発的事故だが、「国家の結末」においてみれば必然の事故である。その必然になにひとつ対応できない組織が国家であり、「近代の結末」だったというあからさまな事態を、いまわれわれは眼前にしている。震災当初は、経験したことのなかった大きな空洞感の中で、慟哭とともに見出そうとしていた可能性と原理的な希望は、いま毎日ひとつずつ消されている。首相の「脱原発』表明が個人的な見解だなどと注釈する議会制に頓着するキチガイじみた政治家らはむろん、真摯に声を出すべき知識人らも同様に悪しき「国家の結末」に手を貸している。この国に二度といい夏はこない。
(映画芸術no.436 〔2011年7月発売〕 編集者「I」の文章)